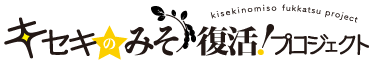2019年10月13日、台風で千曲川の堤防が決壊。小川醸造場の味噌蔵や設備、仕込んだ味噌、大豆畑がすべて濁流に飲まれた
興奮した特殊な心理状態だった。その時の記憶ははっきりしない。
長野市長沼「小川醸造場」代表の小川泰祐さん
経験のない大規模な台風が長野を襲った。雄大な千曲川(信濃川)沿いに位置する長野市長沼地区にある小川醸造場。代表の小川泰祐さん(65)は、家族が避難したあとも自分だけ残った。「まさか水が来ることはない」「大丈夫」と自分に言い聞かせるように、味噌蔵の機器や味噌をできるだけ高いところへ上げる作業に必死だった。
しかし、濁流が一気に押し寄せた。すぐ近くの堤防が決壊した。自宅の2階に駆け上がった。ベランダから見る壮絶な光景を夢中で撮影し、気がつけば自衛隊のヘリに吊り上げられていたー。
数日後の自宅は、一面が泥と水と漂流物に覆われていた。大木や体育館の床材などが突っ込み、建屋が倒壊。中にあった味噌づくりの機材や設備、貯蔵していた味噌が跡形もなく流されていた。

自宅の1階にも濁流の痕跡がはっきりと残っていた。室内に押し寄せた流れは、鴨居にあった遺影のすぐ下で止まっていた。「先代が守ってくれたのかー」。絶望した心に小さな明かりが灯る。
以来、真冬が来るまで、ボランティアといっしょに泥をかき出し、物を出し、背中を押されるように、ひたすら片付け続けた。「あの時みんな捨ててしまったー、もったいなかったかもしれない」と、ポツンと話す。
135年の歴史ある味噌蔵は、地域から愛されるみそ屋さんだった
初代は小川順作さん。農閑期に群馬県長野原の造り酒屋を借りて、日本酒をつくっていた。仕込みが終わったら帰ってくるという行き来を何年も続けていたらしい。明治18年(1885年)に、同じ麹を使う仕事として、醤油と味噌づくりをここではじめた。
二代目は、杜氏として長野市安茂里や小布施町など近隣で酒造りしながら、醤油と味噌の醸造を手掛け、豊野駅から貨車に乗せて東京の問屋へ卸していた。
三代目で小川さんの父・一義さん(大正15年生まれ)は、大学で果樹全般を学び、りんご栽培をはじめた。醤油と味噌は販路が東京から地元に代わり、地域のお客さんとつながっていった。果樹が専門だった父は、醤油の生産をやめ、味噌の生産を息子の泰祐さんに託した。
小川泰祐さんは、四代目になる。父の姿を見ながら味噌をつくることは子どもの頃から身近で、麹をつくる手伝いもした。小学生の頃まで、忙しい時は近所から3~4人が手伝いに来ていたが、撹拌機など次々と機械化が進んでいった時代だった。

モノをつくることへのこだわりは、芸術から生まれた
蔵の中での仕事に閉塞感を感じ、「山の向こうを知りたい」と東京へ進学した。行先は美術大学。油絵を描いていた。時代は高度経済成長。米国の新鋭芸術が日本にも流入してくる。「アメリカで勉強したい」と思いバイトしながらも、お金が貯められず思いを果たせなかった。
縁あって信州の味噌の会社に務め、徐々に軸足が長野へ向く。31歳の時、ここへ戻った。「長男だから」ということもあるが、“絵具とキャンバス”を“味噌と麹”に替え、「ものをつくるという共通した想いがある」と、自分に言い聞かせた。
「信州青年の船」がきっかけとなり、病院で栄養士として勤めていた京子さんに出会う。結婚後、京子さんは栄養士をやめ、この地で3人の子を育てた。畑を耕し、両親のりんご栽培を手伝い、味噌をつくる。そんな日常を、夫婦二人三脚でコツコツと続け、地域にも親しまれてきた。

自ら大豆を育て、微生物の力を信じ、試行錯誤を続けて生まれた味噌
「味噌は寝かし方、温度と状況などで独自性と特徴、魅力が出る」と、小川さんは目を細める。味噌になる前の流れ、微生物の動きを大事にする。塩を混ぜるのは微生物が動くのを待ってから。いろんな菌が出会い関わりあって、複雑な味が生まれるーーまさに芸術だ! しかし、「理想を毎回探しても、いつも見つからないのが味噌づくりの醍醐味だ」と言う。
大豆も、この地域で生産されたものを使いたい。原料の大豆が良くなれば、味噌の品質もぐっと良くなる。自分で育てた大豆での仕込みは、気合いと思い入れが入る。
被災前までの生産量は、年間約10トン。3割は首都圏へ送り、4~5割を地元のお客さんへ届ける。「小川さんの味噌じゃなきゃダメ」という、こだわりのおやき屋やラーメン屋もある。産地直送で地元はもちろん、全国のお客さんともつながってきた。
被災前に出品していた味噌が、日本一に輝く。農水大臣賞受賞の報せが!
小川さんは、長野県味噌工業組合技術会に参加している。県内で味噌づくりをする技術者とともに切磋琢磨して、互いに腕を磨き研究してきた。毎年、仕込み実習をし、鑑評会をめざす。毎回、作戦を練ってのぞみ、結果を次の励みにしてきた。
これまでに2回、全国味噌鑑評会で農林水産大臣賞を受賞した。そして10月30日、3度目の受賞の報せが届く。被災直前の10月7日、500グラム入りカップを2つ、箱に詰めて東京へ送っていた。11月14日に東京・日本橋の鉄鋼会館で表彰式があるという。
朗報なのか実感がわかなかった。まだ地域一面が泥に埋もれていて気分も沈んでいたからだ。手元にあった味噌はすべて濁流に流されてしまった。なにも残っていない。賞の辞退も考えた。「大丈夫だから、受けてくれ」と、農水省から連絡が入った。
家財も何もかも流された。表彰式に履くような靴も流された。あるのは長靴だけ。幸いにも2階のタンスにスーツが残っていた!
泥の世界を脱し、気分転換になるかと思って訪れた表彰式。きらびやかな式場にテレビカメラがあふれ、次々とマスコミの取材に囲まれた。「息抜きどころか大騒ぎ(苦笑)」となり、その日のうちにニュースが流れた。帰りの新幹線で知人から続々とメールが届く。
「受賞はうれしかった。背中を押されているような気がした」と小川さん。しかし、ある意味プレッシャーにもなったのだ。味噌づくりのすべてを流されてしまった。「設備を建て直し、再び同じものをつくれるようになるだろうか」と…。表彰式の夜、喜びの一方で大きな不安に襲われながら、帰路についた。明日からまた、泥と瓦礫の片付けが待っている…。(完)
記録・執筆: ソーシャルライター 吉田百助
構成編集・撮影: ナガクル編集デスク 寺澤順子
※このストーリーは、2020年4月3日、小川さん夫妻へのインタビューをもとに構成編集しました。多くのボランティアの皆さんの協力により片付けが終わり、味噌蔵の基礎解体も終えました。しかし、味噌蔵や設備再建の目処は、未だ立っていません。家財すべてを失い、借家で生活し、収入も絶たれ、苦難の中で、なんとか大豆畑を復活させ、助成金を申請するなど、奔走中です。味噌作りを諦めないで前向きに頑張っています。ぜひ皆様の応援をよろしくお願いいたします。